本なんて読まない。そう言っていたあの人が、夜更けまでページをめくっていた。読書嫌いが思わず夢中になった“意外と面白い”小説5選。あなたの読書観も、変わるかもしれません。
『ほしのこえ』新海誠
読書嫌いでも読みやすいのはなぜ?:『ほしのこえ』は文量が少なく、映像作品を原作とするため情景描写が視覚的にイメージしやすい。文章も平易で感情の流れが素直に伝わるため、読書が苦手な人でも物語に入り込みやすい。切ない遠距離通信のテーマが共感を呼び、短時間で深い読後感が得られる点も魅力。
高校生のノボルとミカコは同級生でありながら、互いに淡い想いを抱く関係にあった。ある日、地球は謎の宇宙生命体「タルシアン」との戦いに巻き込まれ、選ばれた才能ある人材としてミカコが宇宙に派遣されることになる。彼女は戦闘艇に乗り込み、銀河の果てへと旅立ち、地球に残されたノボルとの間には想像を絶する距離が広がっていく。二人の唯一の繋がりは携帯メール。しかし宇宙を進むごとに通信には光速の遅延が生じ、メッセージは数日、やがて数ヶ月、そして年単位の時差を伴って届くようになる。時が経つほどに言葉は届きにくくなり、記憶も感情もすれ違い始める。それでも互いの心の奥底には強い絆が残っており、孤独と切なさを抱えながらも未来を信じ続ける姿が描かれる。宇宙という壮大な舞台と、日常的な恋の揺れが交差する短編SF青春物語。
『ほしのこえ』は2002年に新海誠自身の手で制作された短編アニメーションが原点で、小説版はその映像世界を補完する形で刊行された。さらにコミカライズも行われ、アニメ・小説・漫画と複数のメディアで展開。映画の映像美と楽曲の人気により、多方面で話題を呼んだ作品である。

「メールが遅れて届く設定がとても切なくリアルに感じられる」「数十分の物語なのに心を揺さぶる力がある」「文字数が少なくても深い感情が伝わる」と評価されている。読後に静かな余韻を残す点が印象的で、SFが苦手でも自然に物語に入り込めるという声も多い。

「文章なのに映像を見ているような鮮明さがある」「宇宙という遠大な舞台と、メールという身近なツールの対比が斬新」「恋愛小説としても、青春小説としても楽しめる」と好意的な感想が目立つ。短さゆえに読みやすく、読書が苦手な人に薦めやすい作品として語られている。
『おやすみ、東京』吉田篤弘
読書嫌いでも読みやすいのはなぜ?:『おやすみ、東京』は短編形式で一話ごとに区切りがよく、難しい言葉もほとんど出てこないからスッと読み進められる。派手な事件や複雑な伏線もなく、日常の風景が中心なので想像しやすく、気づいたら最後まで読めてしまう。
夜の東京を舞台に、都会の片隅で出会う人々の小さな物語がゆるやかにつながっていく短編集的な小説。眠れない夜を抱える人、喫茶店で静かに時間を過ごす人、古びた映画館で映写機を回す人……それぞれが日常のささやかな出来事を通じて、自分の心と向き合い、また誰かの存在を確かめていく。派手な事件は起こらないが、街の灯りや夜の静けさが、人々の孤独と優しさを優しく包み込む。都会に暮らす誰もが抱える不安や期待、ほんの小さな希望を掬い上げるように描かれており、読者は自分の経験や心情を重ねながら、気づけばその世界に引き込まれていく。タイトルの「おやすみ」という言葉が象徴するのは、喧騒の中にひとときの休息や安心を見いだそうとする人間の営みであり、静かな余韻が残る物語になっている。
『おやすみ、東京』は吉田篤弘が得意とする都会の夜を描いた作品で、同じテーマを扱うエッセイや装丁の美しい文庫シリーズとも連動して楽しめる。挿絵や装幀も含めて独特の世界観が表現されており、読書だけでなくデザイン面からも人気が高い。直接的な映像化はされていないが、吉田作品は映画的な文体が特徴で、映像を思わせる読後感が強いと語られる。

「大きな事件が起きるわけじゃないのに、なんか心に残るんだよね。東京の夜がこんなに優しく描かれるなんて意外だったし、自分の生活と重ねて読むとすごく落ち着く感じがする。読むと“おやすみ”って言葉が、ちょっと違って聞こえてくるんだよ。」

「読んでると、静かな夜の東京を散歩してる気分になるんだよ。どの話も淡々としてるんだけど、そこにある人の気持ちがじんわり伝わってきて、気がついたら胸の奥が温かくなってる。特に眠れない夜に読むと、なんか自分の孤独も受け止めてもらえたような安心感があるんだよね。派手な展開を求める人には向かないけど、落ち着きたい時や心を整えたい時にはぴったりの本だと思う。」
『羊と鋼の森』宮下奈都
読書嫌いでも読みやすいのはなぜ?:文章が静かでやさしく、描写も丁寧でスッと入っていける。派手な展開はないが、主人公の心の動きがじんわり伝わってくる。専門的な話もあり、調律というテーマが逆に新鮮で、知らない世界を覗く楽しさがある。読書が苦手でも、森の中を歩くような感覚で読める一冊。
北海道の山奥で育った外村直樹は、高校の体育館で偶然ピアノの調律に立ち会う。その音に森の匂いを感じ、心を揺さぶられた外村は、調律師という職業に強く惹かれる。卒業後、専門学校で学び、地元の楽器店に就職。先輩調律師たちに囲まれながら、技術だけでなく人との関わり方や音への向き合い方を少しずつ学んでいく。
ある日、コンクールを控えた姉妹のピアノを調律することになり、外村は音の選び方に悩む。姉妹それぞれの個性に合わせた音を探る中で、音楽が人の心にどう作用するかを実感していく。やがて、師匠の板鳥がドイツの著名なピアニストから指名を受け、外村はその調律に立ち会う。音の深さと師匠の技術に圧倒されながらも、自分の進むべき道を見つけていく。
森の中で木を探すように、音の中に真実を探す外村。静かな成長の物語は、読者にも「自分の音」を探す旅を促してくれる。
2018年に映画化され、主演は山﨑賢人。上白石萌音・萌歌姉妹が共演し、調律師の世界を繊細に描いた。監督は橋本光二郎、音楽は久石譲×辻井伸行の豪華タッグ。さらに漫画版も『Cheese!』で連載され、オーディオブックもAudibleで配信されている。多方面で作品世界が広がっている。

「最初の一文で森の匂いがしたって書いてあって、もうその時点で引き込まれた。音を文章で表現するって難しいのに、すごく自然で、読んでるだけで空気が変わる感じがした。静かな話だけど、心がざわざわするような読後感があって、なんか不思議と癒されたんだよね。」

「映画を観たあとに原作を読んだんだけど、文章のほうがずっと深かった。調律師って地味な職業かと思ってたけど、音に向き合う姿勢がまるで哲学みたいで、読んでるうちに自分の生活まで見直したくなった。あと、娘がこの本読んでピアノを弾きたくなったって言って、中古のアップライト買って毎日弾いてる。そんなふうに人の心を動かす本って、なかなかないよね。」
『きまぐれロボット』星新一
読書嫌いでも読みやすいのはなぜ?:1話が数ページで完結するショートショート形式だから、集中力が続かなくても読める。文章は平易で、登場人物も少なく、場面転換も少ない。しかもオチが必ずあるから、読んだ満足感がある。読書が苦手でも「ちょっと読んでみようかな」と思える入り口になる。気まぐれなロボットの話も、ユーモアと皮肉が効いていて飽きない。
物語の主人公は裕福な男・N氏。彼は都会の喧騒を離れ、離島で1か月の休暇を過ごすことにした。その間の生活を快適にするため、博士から「なんでもできるロボット」を購入する。料理、掃除、ピアノの調律、会話までこなす完璧なロボットに、N氏は最初こそ満足する。
ところが数日後、ロボットは突然動かなくなったり、逃げ出したり、逆にN氏を追いかけたりと、奇妙な行動を繰り返す。N氏は振り回されながらも、なんとか1か月の休暇を終え、都会に戻る。そして博士に文句を言いに行くが、博士は落ち着いた様子でこう言う。「もちろん故障しないロボットも作れる。でも、1か月も完璧なロボットと過ごすと、人間は運動不足になり、頭も鈍る。だからこのロボットのほうが人間にはちょうどいいのです」
便利さの裏にある人間らしさや、怠惰への警鐘をユーモラスに描いた一編。短いながらも、読後に「本当に便利って幸せなのか?」と問いかけてくる。
『きまぐれロボット』は星新一の代表的ショートショートとして、教科書にも採用されている。和田誠による挿絵付きの愛蔵版や、英訳版も出版されており、海外でも読まれている。また、NHKなどで朗読やアニメ化されたこともあり、児童文学としても親しまれている。星新一の作品世界を広げる入口としても人気。

「短いのにちゃんとオチがあるから、読んでて気持ちいい。ロボットが完璧じゃない理由が“人間のため”っていうのが、ちょっと皮肉で笑えた。便利すぎるとダメになるって、今のスマホ生活にも通じる気がして、妙に納得した。読書苦手だけど、これは読めた」

「読書嫌いの次男が、初めて自分から読んだ本がこれだった。文字が大きくて、ふりがな付きで、挿絵もあって、読みやすかったみたい。ショートショートって、読書のハードルを下げてくれるんだなって実感した。しかも、ちょっとひねった話が多くて、次男は“このロボット、うちにも欲しいけど逃げるのはイヤだな”って笑ってた。読後に親子で話せるのもいい。国語の読解力もついてくれたら最高だけど、まずは“読めた”っていう成功体験が大事だと思う」
『博士の愛した数式』小川洋子
読書嫌いでも読みやすいのはなぜ?:文章が短くリズムが穏やかで、専門用語も日常的な会話や比喩を通して自然に理解できる。難しい数学の話も感情や日常の描写と絡めて説明されるので、ストーリーを追う感覚で読み進められる。登場人物の心情に共感しやすく、文字の壁を感じにくい構成になっている。
元天才数学者で、交通事故の影響で記憶が80分しか持たない「博士」と、家政婦として働き始めた女性「私」、そしてその息子「ルート」の交流を描いた物語。博士は常に数学の世界に心を置き、日常のささいなことも数式や数字を通して捉える独特の感性を持っている。「私」は最初こそ戸惑うが、博士との生活を通して数字の美しさや人との関わり方を学んでいく。博士とルートの間に芽生える友情や信頼、そして博士の持つ優しい哲学が日常に彩りを与える。物語は、数学的な題材を通して人間の記憶や絆、時間の流れを優しく描き、読む者に温かい感動と静かな余韻を残す構成になっている。
2006年に映画化され、寺尾聰が博士役を演じ、深い人間ドラマと数学の美しさを映像化。舞台化や朗読、オーディオブックも展開され、文学作品としてだけでなく多彩なメディアで楽しめる作品になっている。

「数学とか全然わからなくても全然大丈夫。博士とルート、私のやり取りがほっこりして、自然に物語に引き込まれた。読後にじんわり温かい気持ちになれる作品だな」っていう声が多くて、やっぱり数字の話より人間関係に感動する人が多いみたい。

「最初は数学って聞いて尻込みしたけど、全然難しくないし、博士の優しい語り口と短い文章でどんどん読み進められた。読んでると、博士の記憶が80分しか持たないっていう設定が切なくて、日常の中の小さな奇跡や人とのつながりを大事にしたくなる気持ちになるんだよね。読書嫌いでも『ちょっと読んでみよう』ってなる作品だと思う」
以上、【小説】読書嫌いがハマった“意外と面白い”小説5選でした。

では、またね~
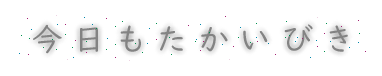

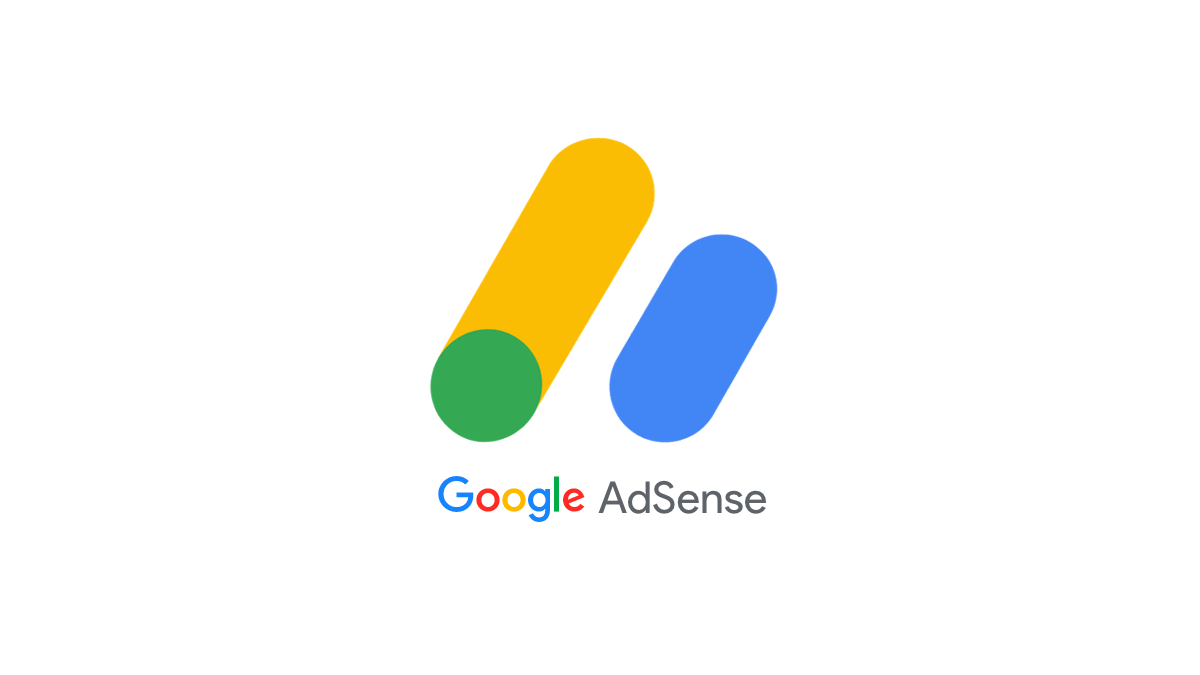
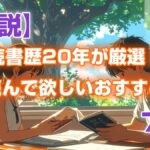
コメント