親が高齢になると、ちょっとした外出や体調の変化が気になる。
電話だけでは確認できないことも多い。
でも、スマホを使えば「見えない不安」が「見える安心」に変わる。
位置情報、通知、健康記録。
難しい操作は不要。家族がそっと見守れる仕組みがある。
見守りの基本:スマホでできること一覧
位置情報共有
Googleマップの「現在地共有」機能
- 親のスマホでGoogleマップを開く
- メニュー → 「現在地の共有」 → 家族のGoogleアカウントを選択
- 共有期間を「常に」に設定すれば、いつでも居場所が確認できる
Life360(無料でも使える見守りアプリ)
![]()
Life360による位置情報の共有
Life360は、大切な人から成るサークルとのつながりを簡単にすることで、日々の生活をシンプルにします。位置情報の共有を使用すると、以下のことが可能になります。 - 友人や家族が今どこにいるかを地図上で簡単に確認できます。- 大切な人が自...
![]()
Life360 - Google Play の Android アプリ
いつでもどこでも、お使いのデバイスで何百万もの最新の Android アプリ、ゲーム、音楽、映画、テレビ番組、書籍、雑誌などを楽しめます。
- 家族全員でグループ(サークル)を作成
- 現在地・移動履歴・バッテリー残量まで確認できる
- 「到着通知」「出発通知」も自動で届く
通知・安否確認
LINEの「定型文通知」+「スタンプ連絡」
![]()
LINE
国内9,900万人※が利用するコミュニケーションアプリ「LINE」「LINE」は、無料で友だちや家族と、トーク(チャット)・音声通話・ビデオ通話を楽しめます。 ユーザー同士であれば、国内・海外・通信キャリアを問わず、いつでも、どこでもリア...
![]()
LINE - Google Play の Android アプリ
いつでもどこでも、お使いのデバイスで何百万もの最新の Android アプリ、ゲーム、音楽、映画、テレビ番組、書籍、雑誌などを楽しめます。
- 毎朝「おはよう」スタンプを送る習慣をつける
- 返信がなければ電話で確認する流れを作る
- 定型文(「今から出かけます」「帰宅しました」)を登録しておくと便利
Google Nest Hub(スマートディスプレイ)
- 室内の動きや音声を検知して、家族に通知
- カメラなしでも「活動があるかどうか」がわかる
- スケジュールや天気も表示されるので、親の生活リズムも整いやすい
健康管理
Google Fit(Android)/Apple ヘルスケア(iPhone)
![]()
Google Fit - Google Play の Android アプリ
いつでもどこでも、お使いのデバイスで何百万もの最新の Android アプリ、ゲーム、音楽、映画、テレビ番組、書籍、雑誌などを楽しめます。
- 歩数・心拍数・睡眠時間を自動記録
- スマートウォッチと連携すれば、より正確なデータが取れる
- 家族がアプリを開いて、記録を一緒に確認するだけでも安心感がある
転倒検知・SOS機能(Apple Watch)
- 強い衝撃を検知すると、自動で緊急連絡先に通知
- 長時間動きがない場合も通知される
- ボタン一つでSOS発信できる
3.高齢者にやさしいスマホとアプリの選び方
スマホ選びのポイント
見やすい画面
- 文字サイズが大きく設定できる
- コントラストが高く、白黒の切り替えがしやすい
- ホーム画面がシンプルでアイコンが大きい
操作が簡単
- ワンタッチで電話・LINEが開ける
- 音声入力で検索やメッセージ送信ができる
- 誤操作を防ぐ「戻るボタン」や「ホームボタン」がわかりやすい
おすすめ機種例
アプリ選びのポイント
見守りアプリは「画面がシンプル」「通知が静か」が基本
- 文字が多すぎると混乱しやすい
- 通知音が大きすぎるとストレスになる
- 設定項目が少ないほうが安心
おすすめアプリ一覧
家族がサポートするスマホ活用術
導入・設定は「一緒にやる」が基本
初期設定のポイント
- Wi-Fi接続、Googleアカウント登録、LINEのインストールなどは家族がサポート
- 文字サイズや通知音量を本人に合わせて調整
- ホーム画面に「よく使うアプリ」だけを並べる
見守りアプリの設定例(Life360)
- 家族グループ(サークル)を作成
- 親のスマホにアプリをインストール
- 位置情報の共有を「常に」に設定
- 通知の種類(到着・出発・バッテリー低下)を選ぶ
通知の使い方と調整
通知は「安心のサイン」
- 毎朝「おはよう」スタンプが届く → 活動開始の確認
- 外出通知 → 予定外の移動に気づける
- 帰宅通知 → 無事を確認できる
通知が多すぎると逆効果
- 通知時間を「朝〜夕方」に限定
- 音量やバイブの強さを調整
- 本人が「うるさい」と感じたら、内容を見直す
困ったときのサポート方法
電話でのサポート
- 「画面の右上にある青い丸を押してみて」など、具体的に説明
- LINEのビデオ通話で画面を見ながら案内する
遠隔操作(Androidの場合)
- iPhoneの場合は「画面共有」や「FaceTime」で案内する
- Googleの「リモートサポート」機能を使えば、家族がスマホ画面を操作できる
見守りは「監視」ではなく「寄り添い」
スマホを使った見守りは、親の生活を管理するためではない。
「何かあったときに気づける」「日々の変化に寄り添える」ための手段。
本人の気持ちを尊重しながら、家族がそっと支える。
それが、スマホ見守りの理想的なかたち。
よくある悩みとその対策
悩み①:スマホの操作が難しい

ユーザー
「ボタンが多すぎて何を押せばいいかわからない」 「LINEの通知が来ても、どこを押せばいいのか迷う」
対策:
- ホーム画面に「よく使うアプリ」だけを配置(LINE、カメラ、電話など)
- 文字サイズを最大に設定
- 音声入力を活用(GoogleアシスタントやSiri)
- ワンタッチで家族に電話できるショートカットを作成
悩み②:通知がうるさい・多すぎる

ユーザー
「ピコンピコン鳴って落ち着かない」 「通知が多くて何が大事かわからない」
対策:
- 通知の時間帯を「朝〜夕方」に限定
- 通知音を優しい音に変更、またはバイブに切り替え
- 見守りアプリの通知設定を「必要なものだけ」に絞る(例:位置情報の変化のみ)
悩み③:位置情報をオフにされてしまう

ユーザー
対策:
- アプリ側で「常に共有」に設定し、変更できないようにする(Life360など)
- 位置情報の必要性を本人に説明し、納得してもらう
- 「見守り=安心のため」と伝えることで、協力的になってもらえる
悩み④:プライバシーが気になる

ユーザー
対策:
- 家族間で「見守りルール」を決めておく(例:毎朝と夜だけ確認)
- 見守りの目的を「監視」ではなく「安心のため」と明確に伝える
- 通知や位置確認は「必要なときだけ」にする
6.実際の使い方シーン紹介
朝の「おはよう通知」
- LINEで「おはよう」スタンプを送る
- 親が返信すれば、活動開始の確認になる
- 返信がない場合は電話で軽く声かけ
ポイント: 「毎朝のやりとり」が習慣になると、安否確認が自然にできる
外出時の位置確認
- Life360やGoogleマップで現在地を確認
- 予定外の移動があれば、LINEで「どこ行ってるの?」と優しく声かけ
- 帰宅通知が届けば安心できる
ポイント: 「見守っている」ことを伝えるより、「気にかけている」ことを伝える方が受け入れられやすい
夜の「無事帰宅」確認
- LINEで「帰ったよ」スタンプを送ってもらう
- スマートウォッチの歩数や活動記録を見て、無理していないか確認
- 体調が気になるときは、Google Fitの記録を一緒に見る
ポイント: 「今日も無事だったね」と声をかけるだけで、親も安心する
週末のビデオ通話
- LINEやFaceTimeで顔を見ながら話す
- 表情や声の調子から、体調や気分の変化に気づける
- 孫の写真や動画を見せると、会話が弾む
ポイント: 「見守り」ではなく「つながり」を感じる時間にする
おわりに:スマホは「見守る道具」ではなく「寄り添う手段」
スマホは“つながり”を支える存在
スマホはただの機械じゃない。 親の生活にそっと寄り添い、家族の安心をつなぐ道具。 通知や位置情報は「監視」ではなく「気づくための仕組み」。 それがあるだけで、離れていても心が近くなる。
見守りの本質は「気づけること」
- 返信がないときに「どうしたんだろう」と思える
- 予定外の外出に「大丈夫かな」と声をかけられる
- 歩数や睡眠の記録から「最近疲れてない?」と気づける
こうした小さな気づきが、親の安心につながる。 スマホはその“気づきのきっかけ”をくれる。
家族で使うからこそ意味がある
- 親がスマホを使えるようになるには、家族のサポートが必要
- 設定や操作を一緒にやることで、親も安心して使える
- 「見守っているよ」と伝えることで、親も心を開きやすくなる
スマホを渡すだけではなく、「一緒に使う」ことが大事。
見守りは“習慣”になると自然に続く
- 毎朝の「おはよう」スタンプ
- 週末のビデオ通話
- 月に一度の健康記録チェック
こうした習慣があると、見守りは特別なことではなくなる。 日常の中に溶け込んだ「安心の仕組み」になる。
まとめ:スマホでつながる、安心が育つ
- 離れていても、スマホがあれば心は近くにある
- スマホは親の生活を支える「寄り添いツール」
- 難しい操作は不要。家族と一緒なら使える
- 見守りは「気づき」「声かけ」「つながり」の連続
今回は、スマホで親を見守る!【高齢者向け安心アプリ編】でした。

hajizo







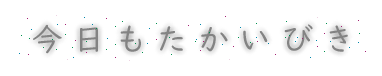



コメント