スマホを使うことで、家族や地域の安全を効率的に守れる。自治体サービスや見守り機能、防犯アプリ、緊急通報の仕組みまで、誰でもすぐに活用できる方法をまとめる。子どもや高齢者の見守り、地域の防犯情報まで幅広くカバーする。
自治体・地域サービス

地域の防災速報を確認する方法
災害はいつ起きるかわからない。地震、台風、大雨など、いざというときに備えて、スマホで防災情報を受け取る方法を知っておくと安心。
主な確認方法
- 自治体公式アプリを使う 多くの市区町村が、災害情報を配信する専用アプリを提供している。地震速報、避難所の開設情報、警戒レベルなどがリアルタイムで届く。 例:東京都防災アプリ、横浜市防災情報アプリなど。
- Yahoo!防災速報アプリ 全国対応で、地震・津波・台風・豪雨・避難情報などを通知してくれる。地域を複数登録できるので、離れて暮らす家族の地域も設定可能。
- LINEで自治体を友だち登録 一部の自治体はLINE公式アカウントで防災情報を配信している。通知がLINEに届くので、アプリを増やしたくない人にも便利。
- 気象庁のウェブサイトやアプリ 詳細な気象情報や警報・注意報を確認できる。速報性は高いが、情報量が多いため、慣れていない人には少し難しいかもしれない。
通知を受け取るためのポイント
- スマホの通知設定をオンにする アプリを入れても通知がオフだと情報が届かない。設定画面で通知を許可しておく。
- 位置情報を正しく設定する 自分の住んでいる地域を登録しておくと、必要な情報だけが届く。複数地域の登録も可能。
- 通信環境を確認しておく 災害時は通信が不安定になることもある。Wi-Fiとモバイル通信の両方を使えるようにしておくと安心。
自治体が提供する見守りサービスとは
高齢者向けの見守りサービス
- 訪問型 地域スタッフやボランティアが定期的に訪問。体調や生活の様子を確認する。
- 電話・メール型 毎日決まった時間に連絡。応答がない場合は家族や支援者に通知。
- センサー型 室内に設置したセンサーで動きを検知。異常があれば通知される。
- 配食サービス型 食事の配達時に安否確認も行う。受け取り状況から体調の変化を察知。
子ども向けの見守りサービス
- 登下校見守りシステム(例:otta、ミマモルメ) ランドセルに小型の見守り端末をつけるだけ。校門や通学路の「見守りスポット」を通過すると、保護者のスマホに通知が届く。 端末は軽量(約8g)で、防水・防塵対応。電池寿命も長く、充電不要のタイプもある。
- 地域協力型 コンビニや商店、タクシーなどに見守りスポットを設置。地域の人が「見守り人アプリ」を入れて協力することで、子どもの通過情報が記録される。
- 緊急通報機能付き防犯ブザー 子どもが危険を感じたときにボタンを押すと、保護者や学校にリアルタイムで通知される。
- 学校・自治体連携型 通学路や校門にセンサーやカメラを設置。通過時刻や位置情報を記録し、保護者に通知。自治体によっては新一年生に無料配布されることもある。
見守り・安全機能

子どもの登下校をスマホで見守る
通学中の子どもを見守る方法は、昔と今で大きく変わった。今はスマホや小型端末を使って、離れていても子どもの動きがわかる時代。親の不安を減らすための仕組みを紹介する。
よく使われている見守りサービス
- otta(オッタ) 小型の見守りタグをランドセルに入れるだけ。通学路や校門に設置された「見守りスポット」を通過すると、保護者のスマホに通知が届く。位置情報は個人特定されず、通過履歴だけが記録される仕組み。
- ミマモルメ ICタグを使った登下校通知サービス。校門を通過すると、保護者に「登校しました」「下校しました」と通知が届く。学校と連携して導入されることが多い。
- 安心ナビ(NTTドコモ) GPSでリアルタイムの位置情報を確認できる。移動履歴や現在地が地図で表示される。スマホを持っている子ども向け。
- ココダヨ 災害時に家族の位置情報を共有できるアプリ。普段の見守りにも使える。緊急時に「ここにいるよ」と通知できる機能がある。
見守りのポイント
- 通知のタイミングがわかると安心 登校・下校の時間に通知が届くと、無事に学校へ行ったかどうかがすぐにわかる。
- 端末は軽くて邪魔にならない ランドセルに入れても違和感がないサイズ。充電不要のタイプもある。
- 地域の協力で精度が上がる 見守りスポットが多いほど、通過履歴が細かく記録される。地域の商店や住民が協力する仕組みもある。
- スマホを持たせなくても使える タグ型やICカード型なら、スマホを持っていない低学年の子どもでも使える。
保護者が気をつけたいこと
- 通知が届かないときは、学校やサービス窓口に確認
- 子どもに「見守られていること」を伝えておくと安心感につながる
- GPS型はバッテリー残量の確認も忘れずに
高齢者や家族の安全を確認する方法
離れて暮らす親や家族の安全が気になるとき、スマホを使えば「見えない不安」が「見える安心」に変わる。位置情報、通知、健康記録など、そっと寄り添う見守りの仕組みを紹介する。
よく使われる見守りアプリ・機能
見守りの使い方シーン
- 朝の「おはよう通知」 LINEでスタンプを送る → 返信があれば活動開始の確認になる
- 外出時の位置確認 Life360やGoogleマップで現在地を確認 → 予定外の移動があれば声かけ
- 夜の「無事帰宅」確認 スマートウォッチの歩数や活動記録を見て、無理していないか確認
- 週末のビデオ通話 表情や声の調子から、体調や気分の変化に気づける
見守りのコツ
- 通知は「安心のサイン」 多すぎると逆効果なので、時間帯や内容を調整する
- スマホの設定は「一緒にやる」 初期設定やアプリの導入は家族がサポートするとスムーズ
- 見守りは「監視」ではなく「寄り添い」 本人の気持ちを尊重しながら、そっと支える姿勢が大切
緊急通報・防犯

緊急時にワンタッチで連絡する方法
いざというとき、すぐに連絡できるかどうかで安心感が変わる。スマホには、緊急時にワンタッチで家族や警察に連絡できる機能やアプリがいくつもある。
スマホ本体にある緊急機能
- Androidの「緊急情報」登録 設定 → 安全と緊急 → 緊急情報 → 名前・連絡先・持病などを登録。ロック画面から誰でも確認できる。
- iPhoneの「緊急SOS」機能 サイドボタンを長押しすると、緊急通報と位置情報の共有ができる。事前に「緊急連絡先」を登録しておくと、自動で通知が届く。
- 緊急通報ショートカットの設定 ホーム画面に「110番」「家族への連絡」などのショートカットを作っておくと、すぐにタップできる。
専用アプリを使う方法
- ココダヨ 災害時や緊急時に「ここにいるよ」と家族に通知。位置情報も共有できる。
- Yahoo!防災速報アプリ 地震・津波・避難情報などを通知。家族の地域も登録できる。
- 防犯ブザーアプリ(例:あんしんナビ) ボタンを押すと大音量の警報+位置情報を送信。子どもや高齢者向け。
- LINEの「定型文送信」機能 「助けて」「今すぐ来て」などの定型文をワンタップで送れるように設定しておくと便利。
ワンタッチ連絡の準備ポイント
- 緊急連絡先は事前に登録しておく
- 通知の許可や位置情報の設定を確認
- ホーム画面にショートカットを置く
- 家族と「どのアプリを使うか」を共有しておく
地域の防犯情報と安全マップの活用法
地域の安全は、知ることから始まる。スマホを使えば、犯罪情報や危険な場所を地図で確認できる。子どもや高齢者の安全を守るためにも、地域の防犯情報を活用しよう。
防犯情報を確認する方法
- 警察署や自治体の公式サイト 「不審者情報」「犯罪発生状況」などが掲載されている。地域ごとの情報が細かく載っている。
- 防犯マップアプリ(例:安全ナビ) 地域の犯罪発生場所を地図で確認できる。通学路や買い物ルートの見直しに役立つ。
- 地域安全マップづくり(学校・自治体・家庭) 子どもと一緒に地域を歩き、「入りやすい」「見えにくい」場所を探して地図にまとめる。危険を見抜く力が育つ。
地域安全マップの作り方(家庭でもできる)
- 白地図を用意する(通学路や自宅周辺)
- 危険な場所、安全な場所を歩いて探す
- 写真を撮る、メモをとる
- 地図に貼って、理由を書く(例:「見通しが悪い」「人通りが少ない」)
- 家族で話し合って、避けるルートや対策を決める
危険な場所の特徴
安全な場所の特徴
- 人通りが多い商店街
- コンビニや交番など、助けを求められる場所
- 「子ども110番の家」などの登録施設
活用のポイント
- 通学前に「安全ルート」を確認しておく
- 危険な場所は「通らない」「時間帯をずらす」などの対策を考える
- 地域の人と情報を共有すると、防犯力が高まる
アプリ・設定ガイド

見守り・防犯アプリの比較と選び方
見守りや防犯のためのアプリはたくさんある。どれも便利そうに見えるけど、目的や使う人によって向き不向きがある。ここでは、代表的なアプリを比較しながら、選び方のポイントを整理する。
よく使われる見守り・防犯アプリ一覧
Life360
![]()
Life360による位置情報の共有
Life360は、大切な人から成るサークルとのつながりを簡単にすることで、日々の生活をシンプルにします。位置情報の共有を使用すると、以下のことが可能になります。 - 友人や家族が今どこにいるかを地図上で簡単に確認できます。- 大切な人が自...
![]()
Life360 - Google Play の Android アプリ
いつでもどこでも、お使いのデバイスで何百万もの最新の Android アプリ、ゲーム、音楽、映画、テレビ番組、書籍、雑誌などを楽しめます。
ココダヨ
![]()
ココダヨ 地震速報・災害情報を通知 位置情報共有・防災アプリ
ココダヨは家族の安心・安全をささえる防災・防犯・地震速報アプリです●ココダヨで何ができるの?・地震や大雨などの災害時に、家族の「現在地」と「安否」を確認する防災アプリとしてご利用いただけます。・気象庁の緊急地震速報と連動しています。 → ...
![]()
ココダヨ - Google Play の Android アプリ
いつでもどこでも、お使いのデバイスで何百万もの最新の Android アプリ、ゲーム、音楽、映画、テレビ番組、書籍、雑誌などを楽しめます。
otta(オッタ)
![]()
otta(オッタ)- 持ち歩ける、親子の絆。
otta(オッタ)は、あなたの大切な人の行動をみまもり、どこに「おった」かがわかる安心をお届けする見守りサービスです。毎日の登下校やお出かけでの子どもの"安全"と、親の"安心"をつなぎます。■ BLEサービス(ottaタウンセキュリティ)...
![]()
オッタ - Google Play の Android アプリ
いつでもどこでも、お使いのデバイスで何百万もの最新の Android アプリ、ゲーム、音楽、映画、テレビ番組、書籍、雑誌などを楽しめます。
ミマモルメ
![]()
ミマモルメ
校門付近などに設置された受信器が、ご家族がお持ちのタグを検知してこのアプリに位置情報を通知します。弊社提供GPSのご契約者は、端末をお持ちの方の移動履歴をこのアプリよりご確認いただけます。【動作確認OS】 iOS 11以降【動作確認端末】...
![]()
ミマモルメ - Google Play の Android アプリ
いつでもどこでも、お使いのデバイスで何百万もの最新の Android アプリ、ゲーム、音楽、映画、テレビ番組、書籍、雑誌などを楽しめます。
Yahoo!防災速報
![]()
Yahoo!防災速報
【Yahoo!防災速報の特徴】・緊急地震速報や豪雨予報をはじめ、さまざまな災害情報をプッシュ通知でいち早くお知らせします。・現在地と国内最大3地点に通知可能。移動中や旅行中も安心です。・アプリ画面上で、現在地や登録した地域ごとに最新の災害...
![]()
Yahoo!防災速報 - Google Play の Android アプリ
いつでもどこでも、お使いのデバイスで何百万もの最新の Android アプリ、ゲーム、音楽、映画、テレビ番組、書籍、雑誌などを楽しめます。
あんしんナビ
![]()
家族の安心ナビ
□■家族の安心ナビとは■□ご家族の居場所がわかるKDDI提供の安心GPSサービスです。お持ちのスマートフォンにアプリをダウンロードすると、GPS機能を使ってご家族の居場所を簡単に探す・見守ることができます。お子さまの学校、塾、習い事の行き...
![]()
家族の安心ナビ - Google Play のアプリ
ご家族の居場所がわかるKDDI提供の安心GPSサービス。お持ちのスマートフォンのGPS機能を使って、ご家族の居場所を簡単に探す・見守ることができます。
アプリを選ぶときのポイント
- 誰が使うかを考える 子ども、高齢者、家族全員など、対象によって必要な機能が変わる。
- 通知の種類を確認する 登下校通知、現在地共有、災害速報など、目的に合った通知があるかチェック。
- 操作の簡単さを重視する ボタン1つで使えるか、設定が複雑すぎないか。高齢者やスマホ初心者にはシンプルなものが安心。
- 電池の持ちや端末の負担も見る GPS型は電池を消耗しやすい。タグ型なら充電不要で扱いやすい。
- 家族で共有できるかどうか グループ機能があると、複数人で見守れる。通知も共有できる。
選び方の例
- 小学生の登下校 → ottaやミマモルメ
- 離れて暮らす親の見守り → Life360やココダヨ
- 災害時の情報収集 → Yahoo!防災速報
- 緊急時の通報 → あんしんナビやスマホ本体のSOS機能
スマホ初期設定と通知管理のポイント
アプリを入れても、設定がうまくできていないと通知が届かない。スマホの初期設定と通知管理は、安心を守るための基本。ここでは、見守り・防犯アプリを使う前に確認しておきたいポイントをまとめる。
初期設定でやっておくこと
- 位置情報をオンにする 設定 → プライバシー → 位置情報 → アプリごとに許可。見守りアプリは「常に許可」が必要な場合もある。
- 通知を許可する 設定 → 通知 → アプリを選んで「通知を許可」にする。音・バナー・ロック画面表示なども選べる。
- 緊急連絡先を登録する iPhone → ヘルスケア → メディカルID → 緊急連絡先を追加 Android → 設定 → 安全と緊急 → 緊急情報を登録
- バッテリー最適化を解除する 一部のアプリは、バッテリー節約機能で通知が止まることがある。設定 → バッテリー → アプリごとに「最適化しない」に変更。
- アプリのバックグラウンド動作を許可する 設定 → アプリ → 対象アプリ → バックグラウンド動作を許可。通知が届かない原因になりやすい。
通知管理のコツ
- 通知が多すぎると逆効果 必要な通知だけをオンにする。災害速報は「警戒レベル以上」など絞り込みができる。
- 通知音は聞き取りやすいものにする 高齢者には、短くてはっきりした音がわかりやすい。音量も確認しておく。
- 通知履歴を確認する習慣をつける 通知を見逃したときは、通知センターや履歴から確認できる。毎日チェックする習慣があると安心。
家族で共有しておくと安心
- 「通知が来たらどうするか」を話し合っておく
- スマホの設定を一緒に確認する
- アプリの使い方を紙にまとめておくと、高齢者にもわかりやすい
注意・トラブル対策

個人情報を守るための注意点
スマホは便利だけど、個人情報がたくさん詰まっている。名前、電話帳、位置情報、写真、SNSの履歴など、知らないうちにアプリに渡っていることもある。安心して使うために、まずは「何を守るべきか」「どう守るか」を知っておこう。
よくある情報の流出パターン
- アプリが勝手に位置情報や連絡先を取得している
- 無料アプリに広告用の追跡機能が入っている
- 偽の警告画面にだまされて、個人情報を入力してしまう
- 不審なリンクをタップして、詐欺サイトに誘導される
- Wi-Fiの共有設定が甘くて、通信内容が盗まれる
守るためにやっておくこと
- アプリは公式ストアからだけ入れる Google PlayやApp Store以外からのインストールは避ける。偽アプリが混ざっていることがある。
- インストール前に「プライバシー情報」を確認する 位置情報、連絡先、カメラなど、何を取得するかが書かれている。必要以上に情報を集めるアプリは避ける。
- 不要な権限はオフにする 設定 → アプリ → 権限 → 位置情報、カメラ、マイクなどを見直す。使っていないアプリは削除する。
- セキュリティアプリを入れておく ウイルス対策や不正アクセスの検知ができる。携帯会社が提供しているものもある。
- OSとアプリは常に最新にする 古いバージョンはセキュリティの穴がある。自動更新をオンにしておくと安心。
- 怪しいリンクは絶対に開かない 宅配業者や銀行を名乗るSMSやメールに注意。公式サイトから確認する。
見落としがちなポイント
- 天気アプリや懐中電灯アプリでも位置情報を取っていることがある
- 無料アプリは広告収入のために情報を集めていることがある
- SNSの「ログイン連携」で他のアプリに情報が渡ることがある
- アプリの利用規約やプライバシーポリシーは読みにくいけど、最低限の確認は必要
アプリトラブル時の対応と相談先
アプリが動かない、勝手にインストールされた、スマホが乗っ取られたかもしれない…。そんなときは、あわてずに「何が起きたか」「どこに相談するか」を整理して動くことが大事。
よくあるトラブル例
- アプリが急に起動しなくなった
- 勝手に広告が表示されるようになった
- 知らないアプリがインストールされていた
- スマホが勝手に操作されているように感じる
- 個人情報が漏れたかもしれない
自力でできる初期対応
- スマホを再起動する 一時的な不具合ならこれで直ることもある。
- アプリを削除して再インストールする キャッシュや設定が原因の場合はこれで改善する。
- 不要なアプリを削除する 使っていないアプリがバックグラウンドで動いていることもある。
- セキュリティアプリでスキャンする ウイルスや不正アプリを検出できる。
- パスワードを変更する SNSやメール、銀行アプリなど、乗っ取りの可能性がある場合はすぐに変更。
相談先一覧(状況別)
トラブル時のコツ
- 証拠を残しておく(スクリーンショット、日時、アプリ名)
- すぐに誰かに相談する(家族、知人、サポート窓口)
- 放置しない。早めの対応が被害を防ぐ
- アプリの評価やレビューも確認しておくと、同じトラブルに遭った人の情報が見つかることもある
スマホは、子どもや高齢者、地域の安全を守る強力なツールになる。自治体サービスや見守りアプリ、防犯情報をうまく活用することで、日常生活での安心を確保できる。個人情報や権限管理にも注意しつつ、家族全員で安全な使い方を心がけよう。

hajizo












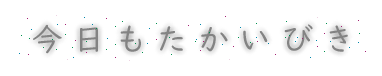


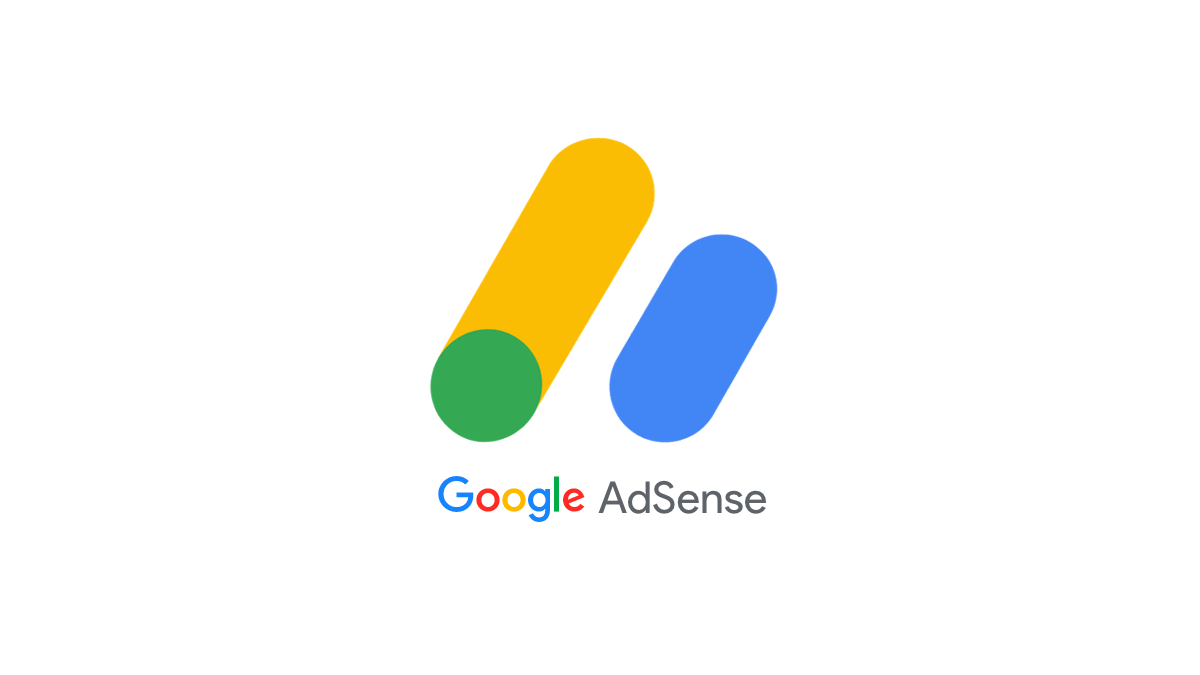
コメント